私の読書 2009年のベスト10
第1位 |
リチャード G ウィルキンソン 格差社会の衝撃 | 単に健康と格差の問題についての本と思って読み始めたが、それにとどまらなかった。米国では収入格差の大きい州ほど健康状態が悪く、それは高収入の人にも及ぶという意外な事実。バングラディッシュとニューヨークハーレムでは平均収入には大きな差があるのに平均寿命はほとんど同じという指摘など意外な事実が次々に示される。そして格差の大きいところでは人は誇りを維持するために大きなストレスを受けそれが健康被害に通じると説いている。 人類は猿からの進化の過程で、ヒヒのような序列社会と、ボノボのような平等な社会とどちらも可能なように進んできたが、未開社会の調査では狩猟社会では平等な社会が圧倒的に多い。その戦略こそが人類の取るべき道だと主張している。 ジャレド・ダイアモンドの著作を思い出す大きな物語を持った主張が快かった。 |
 |
第2位 |
沈復 浮生六記 | 清は乾隆年間の貧しい読書人による愛妻記だが、2人のエピソードの至福感が強いだけに妻を偲ぶ文章には哀切感が満ちみちている。彼は13歳の時10ヶ月年上の陳芸を見初め、その時見せてもらった詩に感動した。この人しかいないと思い詰た彼は、母の賛成を得て婚約する。いとこの結婚式の時、貧しい彼女は無地の簡素な服を着ていたが靴だけはきれいに刺繍があるのに気づき彼女に尋ねると自分で作ったとのこと、眼前に浮かぶような恋の情景である。 貧しい中、友人たちを招き、名園を訪ね、あるいは男装して2人で夜の街に出たりすることが生き生きとえがかれる。しかし、両親の誤解や弟の裏切りや貧困の中、妻は健康を徐々に害して亡くなってしまう。 ささやかな物語だが、人間の温かさと社会の冷たさを描いて忘れられない作品になった。 |
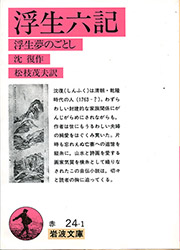 |
第3位 |
ウィリアム・トレヴァー 密会 | アイルランドの現代作家による短編集、ジェイムス・ジョイスの「ダブリン市民」を思い出させるほどのリアルな人間観と、非情な中にあるかすかだが確実な暖かみでじわっと来てしまった。あまりに良かったので刊行されている短編集「聖母の贈り物」「アフター・レイン」も読んで満足したが、翻訳の良さも含めて「密会」がベストだった。 |
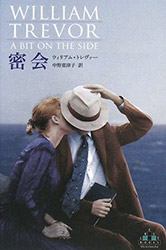 |
第4位 |
イサベラ・バード 日本紀行 | 明治初年に東北から北海道を女性一人で旅したイギリス人女性の旅行記。馬や駕籠、徒歩による旅は現代から想像もつかないほど困難だったことがよくわかる。著者のキリスト教的な価値観が時には鼻につくが、仏教僧との対話などでもその言質はとても公平に感じられる。 旅館の障子穴を開けて覗いたり、旅館の前の屋根にスズナリになって見物する日本人の物見高さにはうんざりもするが、治安の良さ、馬方や駕籠かきが誠実でぼらず献身的なことに感動している。またアイヌの村では彼らの魅力をたたえると同時に、アルコールにおぼれる彼らを残念に思っている。 日本旅行の後、日本の進出が進む朝鮮を彼女は4度訪れて書いた「朝鮮紀行」も読んだ。両班階級の腐敗で沈滞し活力を無くした朝鮮民衆の姿と、対象的にロシアに移民した彼らの積極性とエネルギーを対照的に描いているところが印象に残った。また日本の朝鮮における改革を評価しながら、日本がいかに朝鮮民衆から嫌われているかを描き、秀吉の朝鮮侵略の記憶が朽ちないことがわかる。2編を読むと当時の極東の民衆の心にじかに触れられる気がする。 |
|
第5位 |
ホメーロス オデュッセイア | あまりにも有名な世界の古典だが、意外にも本当におもしろい。まるでインディジョーンズだが、人間性に対する感覚はとてもクールだ。そして古代らしく血なまぐさくとことん徹底している。 | |
第6位 |
ドーデ プチ・ショーズ | 南仏の作家の自伝的小説。とにかく熱っぽい。家族の愛、親身になってくれる友人、主人公を利用して恥じない同僚、リアルなのにダイナミックで楽しい。 | |
第7位 |
ミッシェル・ウエルベック 素粒子 | 現代に甦ったセリーヌといった感じ。露悪的でめまぐるしくてそして寂しい。くどいぐらいに描かれる人間の欲望がやがて戯画的でおかしくなる。ただ救いに至る最終章は無いことにした方が私には良かったが。 | |
第8位 |
ムージル 寄宿生テルレスの混乱 | 男子寮でのいじめと性の目覚めを哲学的内省で描いた小説。不思議な味だ。 | |
第9位 |
カズオ・イシグロ わたしを離さないで | 近未来の臓器移植をテーマにしているが、そのモチーフは閉鎖社会の人間関係の微妙さと、神と未来のない中での希望の問題であるように思った。結局は我々も「死にとらわれている」ところは主人公たちと何ら変わりはないのだし。 | |
第10位 |
ジャン・ジェンペル カテドラルを建てた人びと | 12~13世紀のフランス、パリを中心とするイルドフランス地方から新しいゴシック様式の大聖堂の建設が始まった。それを支えたのは勃興する都市の住民であった。聖職者とも王侯貴族とも違う彼らのエネルギーが伝わって来る。一つの大聖堂を支えた人口の少なさにも驚かされた。 |
2002 |