私の読書 2010年のベスト10
第1位 |
W・G・ゼーバルト 移民たち | W・G・ゼーバルト(1944-2001独)の小説に初めて接したのは4つの短編からなる「目眩まし」だったが、最初の1編につまずき長らく放置してあった。しかし、つまずきの最初の作品を飛ばして2つ目から読み始めたら止まらなくなり、彼の全小説4編を続けて読了してしまった。 何気ない導入部から延々と脱線を繰り返しながら、次々にエピソードが語られてゆく。心温まる幼い頃の思い出と思えば、それは時代と人々の忘却によって痛めつけられた人の記憶につながってゆく。苦しんだ人はいやされる事無く放置され滅んでゆく。その滅びの中にしか本当に真っ当なものは残っていないように感じられてくる。 語り口は軽いが、絶望感はページを追うに従ってつのってゆく。4編のうち、どれを選んでも良かったが明るさと暗さのバランスでまだ明るさの残る「移民たち」をここにあげてみた。 「目眩まし」はカフカやスタンダールの旅から導入していてゲーム的な感じもして楽しさもある。 「移民たち」は暗い森を歩きながら時々日だまりに出会うような美しさが残っている。 「土星の環」は滅びそのものの美しさしか残っていないようなイーストアングリアを歩きながらひたすら脱線と無念が繰り返される。 「アウステルリッツ」は4編の中で一番長く一番救いが少ないだろうか。どれも美しく辛い文学だ。 |
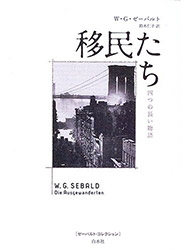 |
第2位 |
ルイス・セプルべダ パタゴニア・エキスプレス | 自ら入獄していた絶望的なチリ軍事政権下の獄内のエピソードを描きながら、どこまでも明るい語り口、その楽天性はその後のエクアドルやパタゴニアの旅でも常に発揮される。人間の見方がちょっと皮肉を含みながら常に快い、既成の概念では全く人を評価しないからだ。 自らのルーツを尋ねて訪ねるスペインへの旅でのエピソードでは、祖父ののふるさとの人との出会いがうらやましい |
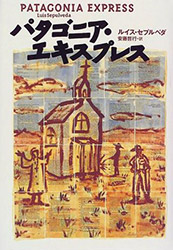 |
第3位 |
ローソン短編集 | 名前も知らなかったオーストラリアの作家(1867-1922)の短編集。舞台はオーストラリアのブッシュ(疎林地帯)。そこに生きる人の素朴さが抑えた筆致で、時にはおかしく、時には悲しく語られる。 以前筒井康隆が紹介していた記憶がある「爆弾犬」はまさに抱腹絶倒のお手本だし、最も好きな「心のこもった作り話」は、大山史郎が「山谷崖っぷち日記」で描いた、本当の意味での侠気というものを具現しているようだ。「帽子まわし」は、誠実という事の本当の意味を教えてくれるようだ。 |
 |
第4位 |
残雪短編(暗夜他) | 1953年中国湖南省生まれの女流作家残雪を池澤夏樹個人編集世界文学全集の1巻で初めて読んだ。7つの短編がおさめられているが、どれも「奇妙な味」のするものばかりだ。 残雪が作った世界で起こる事に何の意味があるのか、その世界に住む人たちが何をしているのかがよく判らないながら、やっている事は細部までのリアリティがあるのだ。世界の構造そのものが現実世界と相当ずれていながら、そのずれが簡単に分かるような何事かを指し示したり、暗示などしていないのだ。しかし、こんな世界だってあるのだと妙に納得させる語り口がある。そこに登場する人はその世界をそのままただ受け入れているのだ。 カフカの不条理の世界では、その構造については納得できる事が多く、そこに投げ込まれた人の巻き込まれる状況が不条理のように見える。そして、主人公はそれに抗おうとしながら無力でいるしかないように感じる。不条理の日常性が残雪ではより深い印象だ。
|
 |
第5位 |
ハインリッヒ・ベル短編集 | 今あまり戦争文学戦後文学は読まれないし,ドイツの作家ハインリッヒ・ベルも過去は読まれたかもしれないけれど現在の日本ではあまり読まれないのかもしれない。だが,誠実に書かれた文学は読む側に襟をたださせるような気持ちにさせる力がある。 実際に戦闘に参加した作者の書いた戦争文学は日本でも海外でもそうだが,ユーモアと偶然が鳴り響いている。特にベルのユーモアは哄笑というような物でも、くすっとした笑いでもなく、大まじめに行われる事のばかばかしさ笑わざろうえないと言ったたぐいの物のようだ。 この短編集で最も心に残ったのは「正義の人ダニエル」ここでは戦争は遠くの雷のように現れるだけだが、主人公の苦しさは戦争を知らない私にも確実に伝わる。 おかしさの極みは「ムルケの沈黙収集」放送局を揶揄して現代に通じている。美しさでは「長い髪の仲間」簡潔そのものの恋愛の描写が美しい。悲痛さでは「ローエングリンの死」占領下の子供の死の悲しさは,戦争は兵士のもだけではない事をはっきりと描いている。 その後読んだ同じ作家による長編「アダムよ おまえはどこにいた」も連作短編のような形で第2次大戦末期の兵士としてのエピソードを語ってゆく。戦争の中の兵士の無力感をこれでもかと書き綴っている、偶然に配当される死、好きになった女性もただ強制収容所に連れて行かれるだけ、作家は救いもカタルシスも誠実に描かないが、そこかにユーモアの影が漂っている。 |
 |
第6位 |
色川武大 怪しい来客簿 | 巧みな語り口にやられてしまう。虚実皮膜の間とは舞台について言った言葉だが、色川武大の藝はそういう感じだ。ある人間の魅力と弱点を厳しく同時に描きながら、その人を好きだと言っているようだ。 |  |
第7位 |
ズーデルマン 憂愁夫人 | 1887年に発表されたドイツの自然主義小説。人一倍の克己心と家族への愛を持ち自己犠牲的な献身をする主人公パウルは恋愛においてもその他総ての事について自己肯定感を持つ事が出来ない。 彼の努力と謙虚さはかえって周りの物を増長させてしまう結果になってしまう。しかし、最後に彼の唯一の理解者によって救われるという波瀾万丈の小説で日本の自然主義小説とは大分違う印象を受けた。 人物は造形は誇張されているが、公平でリアリティがあり一方的な悪人も善人もいないので「ああこういう人いるいる」と非常に納得できそこがこの小説の最大の魅力だった。 神のような性格は周囲の弱い人たちをかえって混乱させるという印象は作者の意図した所ではないかもしれないが強く感じた。 |
|
第8位 |
イアン・マッキューアン 贖罪 | もう少し薄皮一枚で嘘になってしまう、安っぽくなってしまう一歩手前でかろうじてとどまって書かれた小説で、上手さに感服してしまう。中期以降の三島由起夫だとその薄皮1枚こちらに突き抜けて嘘に感じられて私には苦手なのだかそこに限りなく近づきながらまだ大丈夫という印象を持った。 戦争の描写、戦時下の病院の看護婦の生活の描写本当に上手でうっとりするほどだ。そして癒しを与えるような振りをしながら裏切る手口も見事だ。これ又虚実皮膜の間をメタ小説のスタイルも入れながら成立させている。 |
|
第9位 |
エドワード・O・ウィルソン 生命の多様性 | 生物多様性の基礎的な事を丁寧に分かりやすく書いてあり、時々目から鱗が出現し読んでいて楽しい。アリのグループの繁栄の話等びっくりする事も多い。 | |
第10位 |
ギュンター・グラス ブリキの太鼓 | あまりにも有名な世界文学の名作、遅ればせで読んだがとにかく面白い。文庫本3冊最後まで全くだれない力はただ者ではない。人はおかしく悲しい。 | |
番外 |
ヴィルヘレム・グレンベック 北欧神話と伝説 | リストを作ったときに読んだのを失念していたので番外に入れます。5位前後に入れても良い位面白かった。圧巻はアイスランドのサガからの復讐譚、両家の抗争によって双方とも衰えて行く怖さ、略奪された花嫁が子供を育て上げた後にする復習。寛容の薄い社会の恐ろしさが圧倒的に迫ってくる。 | |
番外 |
タッソ エルサレム解放 | 上記と同じ理由でリスト落ち、7,8位には入れたい。イタリア16世紀の叙事詩をジュリアーニが読みやすい形に再編したものが岩波文庫から出ている。十字軍のエルサレム侵攻を舞台に、イスラムの女戦士や妖術を使う姫君と十字軍騎士との恋、十字軍の騎士同士の功名争いや嫉妬がこれでもかと展開する。敵も味方も情念にあふれていて心をとらえるが次々に死んでゆく。双方の登場人物の個性と魅力が際立っていて、作者が宗教裁判を恐れながら書いたというのもうなづける。 |
2002 |