私の読書 2011年のベスト10
第1位 |
マルグリット・ユルスナル とどめの一撃 | 久々に読んだ、くりかえし読みたくなる恋愛小説。ボルシェビキ革命の内戦を背景に、バルト海沿岸の小さな村で完璧な悲劇が成就する。 主人公の2人は心のすれ違いを繰り返すが、その一つ一つの過ちがたとえ無かったとしても悲劇にまっしぐらに向かう事は約束されているような息詰まる印象がある。話者は数十年前の回想として書いているのに何一つ心中は浄化もされずに悲劇は悲劇として心の中に沈溺したままである。 少しも甘くない美しく残酷な小説、ユルスナルを今まで読んでいなかった事を後悔してしまった。 |
 |
第2位 |
プリーモ・レーヴィ 溺れるものと救われるもの | アウシュビッツの生存者、ユダヤ系イタリア人のプリーモ・レヴィが書いたアウシュビッツについての報告と考察。同じ作者の「休戦」(これはソ連軍似よる解放から故国への帰還までの1年近い時間についてかれたもの、出てくる人物像が惹き付ける)「アウシュビッツは終わらない」(ここではなぜ脱走しなかったのか、なぜ反乱を起こさなかったのかという素朴かつハリウッド映画に毒されたような発言に対しても丁寧に答えていいる)も読んだがいずれも、尋常ではない迫力で人間について語っている。どれをここにあげても良い同じレベルの作品だと思う、 生き残ると言うのはきれいごとではない、極寒の地での屋外労働のユダヤ人収容者への食事の配給は900Kcalほど、これではすぐ病気になりガス室に選別されるので、いかにしてそれ以上の食料を確保するかが生きる為には必須なのだ。 その中でどういう風に生き残り、どういう風に溺れていったかが語らる中で人間と言う物の不思議さ哀れさ強さが捉えられている。 |
 |
第3位 |
マルグリット・ユルスナル 黒の過程 | とどめの一撃の次に読んだユルスナルの長編小説、まさに一分の隙もないというのはこういうことを言うのだと思わせる緊密な文章が続き、一行も無駄な箇所を感じない完璧な小説の印象がした。だからといって軽やかな語り口もあれば、ユーモアもある。「とどめの一撃」に感じた燃えるような熱に対して、周りは真っ白で冷えきっているように見えるのに中は真っ赤な熾き火のようだ。 主人公のゼノンは16世紀フランドルの豊かな商人の跡継ぎだったが、その地位を捨て修道僧になり同時に医者として活動する。貧しい庶民に対する共感と、半知性的な事に対する侮蔑という時には矛盾する物の見方が複雑な彼の性格を与えていて、それは作者自身にもつながる物だと思う。時代に抗しながら、それをあから様には出さないでいるのだが、ついには悲劇に向かってしまう物語が哀しい。 作者の「ハドリアヌス帝の回想」も主人公の性格こそ大きく違うが弛みの無い小説ですばらしかった。 |
 |
第4位 |
エミール・マール ヨーロッパのキリスト教美術 | 判りやすくて、説得力があり、かつそうなんだと目を開かれる事の多いロマネスクからゴシック、ルネサンス、バロックといたるキリスト教美術の概説書。図版が無いのが残念だが、ヨーロッパでたくさん回った教会の記憶と、他の写真集等も見ながらたっぷり楽しんで読めた。 カソリックの正統にシンパシーが強い事が少しだけ気になるが、美術とその背景の世界観、そして具体的な図像がどういう風に広がっていったかが丁寧に語られる。 現代美術の自己表現とは対極にある、伝統と先例を尊ぶ表現なのだが、それがこんなにも心を打つということは、現代の新奇を尊ぶ芸術はどこかで歪んでしまったのではないかと考えさせられた。 |
 |
第5位 |
アストゥリアス グァテマラ伝説集 | グアテマラ人の作家が再構築したマヤの民話。今まで一度もであった事のない奇妙なイメージが充満していて驚きだった 「水平線の流れ」「吹矢筒の水晶の腕」「空虚な鳩のみえざる女神」「欺瞞鏡の巨大なる唾」「無価の宝物の商人」というような視覚的でシュールなイメージが鮮烈に美しい。 ある物語では主人公のアルメンドロ博士は財宝をまとった神官であり、森の中を歩く樹であるのだか、自分の魂を色の違う4つの道に与えてしまう。そのもらった魂の四分の一を黒い道は無価の宝物の商人に与えてしまう。商人はその魂で奴隷女を買うが嵐が来て商人は地に飲まれ彼女だけが生き残る。その後博士と彼女は再会するが王にとらえられ魔術師として火あぶりの刑が宣告される。獄中博士は女の腕に船の入れ墨をしてその船で脱獄する。細部に満ちているのイメージが美しい光のきらめきを私の頭の中に作ってくれた。 |
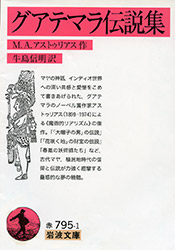 |
第6位 |
与謝野晶子 みだれ紙 | あまりにも有名な歌集だが、通読は初めて。触れる色彩感と熱、情熱にドライブされて読み通すのが他の歌集のように苦にはならなかった。 表現のパターンや作者を巡る状況等の注を読まないと内容が取れない物も多いのだが、意味が分からない段階でも煌めくような印象が魅力的だった。 |
 |
第7位 |
内澤旬子 世界屠畜紀行 | 屠畜を求めて世界を巡り、その現場に飛び込んで見届けて、そこで働く人の生の声を聞いて、世界で屠畜と言う事について差別があるかどうかも探った痛快かつ労作だと思う。文庫版で読んだので、作者自身による丁寧なイラストが小さくて醜かったので残念、ハードカバーが欲しくなった。 尋ねた場所は、韓国 バリ島 エジプト チェコ モンゴル アメリカ 国内では芝浦屠場と沖縄、必ず屠畜を間近でみて、血、皮、内蔵等々無駄なく皆利用する所を見届けているのだ。 語り口は明るいが、「かわいそう」と言って目を背けながら、平気で肉を食べ皮を利用している人への目は厳しいし、血が出るから残酷と言うような「動物愛護運動」にも疑問を投げかけている。 一貫した視点が気持ちが良く説得力のある本だった |
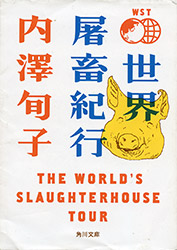 |
第8位 |
シュトルム ハンス・キルヒとハインツ・キルヒ | ロマンティックな小説で知られるシュトルムだが、晩年にかかれたこの本の3編の中編は愛故の人の苦しみを扱って哀切きわまりない。 「聖ユルゲンにて」は分かれた許婚同士が、お互いに好きなまま数十年合えずに時間が経過し、さいごに彼がふるさとの街へ彼女を尋ねるが.... という話。この話は哀しいが清澄でロまだマンテックと言えるのだろう。 「後見人カルステン」は安定目当てで結婚した美しい妻の事を、最初のお産で亡くなった彼女の事を忘れられない夫が、そのだらしない息子を、愛した妻の忘れ形見として援助し続けて破滅していく物語、彼の養女もその息子を愛していて財産を失ってしまう。愛されなくても気持ちが通じなくても愛し続ける2人の姿が哀れだ。 最後の一番長い「ハンス・キルヒとハインツ・キルヒ」が最も心に響いた。努力によって町での地位を気づいた父ハンスは息子ハインツに期待する所が大きいが彼は必ずしもそれに答えられない。恋人を残してかれは町を出て長い事かえらない。彼からの手紙を切手が不足だと言って父は読まずに返却する。しかし、その後反省して彼の噂を聞いて連れ戻すのだが、既に恋人は結婚していた。あまりに容貌の変わった息子は偽物ではないかとの疑念が父に浮かび、息子は手切れ金を拒絶して出て行ってしまう。最後全ての人の孤独感だけが残る。寡婦になった元の恋人と一人になった父が一緒に散歩するシーンが寂しい。聖書の放蕩息子の帰宅を思い出せる物語だった
|
 |
第9位 |
ブラスコ・イバニェス 蘆と泥 | バレンシア近郊の貧しい半農半漁の村を舞台に繰り広げられる愛とお金の物語、頑固な祖父、勤勉な父、地味でおとなしい養女、遊び人の息子、そしてお金持ちの後添いに入った美女が織りなすストーリー性豊かな小説らしい小説。人物の造形が単純でなく根から悪い人間も、完璧に善良な人も存在せず、泥臭いリアリティがたまらない。風土の雰囲気も良く出ていてバレンシアをもう一度訪ねたくなった。 |  |
第10位 |
コーマック・マッカーシー ザ・ロード | アメリカ人の後輩に勧められて読んだコーマック・マッカーシー、生物の息絶えた核戦争後?のアメリカを南を指して移動する父子の物語。メル・ギブソンの映画のように格好いいいことは何も起こらないが、練り込まれた細部がすばらしく退屈せず終わりまで読んでしまった。ラストを救いととるべきなのだろうが、冷静に考えるとあまりにも頼りない。 同じ作者の「全ての美しい馬」も良かったが、恋愛のシーンにはあまり魅力を感じなかった。男同士の関係になるととたんに筆が冴える印象。 |
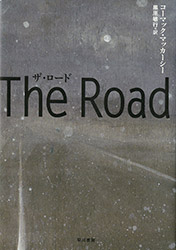 |
番外 |
張岱 陶庵夢憶 | 明末清初の知識人張岱は科挙受けて出仕せず、大きな財産を趣味に生きた人。明松の動乱で財産を全て失うが、その懐旧の気持ちを書いたこの本には後悔も、いじける所も全くなく清々しい。 俳優を自家で雇って芝居を演出し、皆に見せる話、茶とそれを入れる水についての蘊蓄、品種改良を指導した絶品のみかんを今は食べられない話、作庭、祭、旅行等趣味の話に終始している。 清に対しての戦いに財産を投じて参加した話等の自慢話は皆無なのが気持ちがよい。 |
 |
2002 |