私の読書 2012年のベスト10
第1位 |
ダニエル・エヴェレット ピダハン | 著者はピダハンと言う民族の言葉に聖書を翻訳するためその村に家族で暮らし言葉を学んだ |
 |
第2位 |
渡辺京二 黒船前夜 | 江戸時代、北海道をめぐるアイヌ民族、松前藩、幕府、日本商人、ロシア商人、ロシア政府の関わりを資料を丁寧に読み込んで冷静にそして公平に解き明かしている。 |
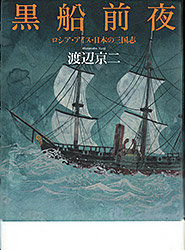 |
第3位 |
前田哲男 戦略爆撃の思想 | 一般市民を標的にする戦略爆撃はナチスによるゲルニカ爆撃がその端緒であった。その後日本海軍を中心とする2年に渡る重慶爆撃によって大々的なものとなった。この地に駐在いた米軍顧問将校により、木造家屋に対する焼夷弾爆撃の有効性が確信され日本爆撃の準備がなされるようになった。 |
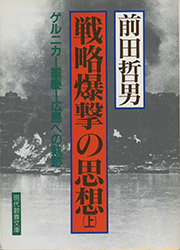 |
第4位 |
トーマス・マン 魔の山 | 大学時代ドイツ史専攻の友人に面白いといわれ古本で文庫4冊をまとめて買ったのだが1冊目も終わらす挫折、40数年ぶりに再チャレンジしたら面白くてやめられなくなった。 前半ではうぶな主人公の女性に対する戸惑いが詳細に描かれている。目のつり上がった東洋的な美女がその対象だが他のトーマス・マンの短編にも同じタイプの女性が描かれていて著者の好みを具現化したものかとちょっと微笑ましい。後半は一転、いろいろな思想のバトルが登場人物によって闘わされ主人公はその中で戸惑って行く。たっぷり理屈っぽくそれがたまらなく面白い。 |
 |
第5位 |
三野正洋 働かないアリにも意義がある | 働き者の代名詞が働きアリだが、しっかりと調べると通常は半分のアリは働いていない。そこでその働かないアリを巣から取り除くと、残りの半分はまた働かなくなる。この意味を説き明かしてくれるところがとても気持ちよい。驚かされる科学の本を読むのは気分転換には最適だががそれにぴったりの本だった。もう少し詳しく書いて欲しかった所も有るが。 |
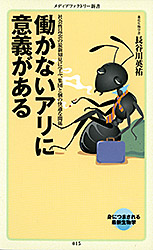 |
第6位 |
伊藤聡 神道とは何か 神と仏の日本史 | 知人の著作、神道の曖昧さに興味が有りそれなりに神道についての本も読んで来たが、この本は新書とも思えぬ濃厚さが詰まっていてその全体像を見せてくれて面白かった。 |
 |
第7位 |
伊勢崎賢治 武装解除 | きれいごとでは済まない内線の武装解除、悪党をも平和の担い手として立てないと内線は終わらないし武装解除も出来ない。正義を優先してばかり入られない状態の中で現実的に平和を取り戻す仕事をしている著者のリアルなやりかたがとても痛快に感じられる。その一方日本の外務省やマスコミは組織の制度として危険な所では働かせない行かせないという状態があかされ唖然とさせられる。 |
 |
第8位 |
フラバル 厳重に監視された列車 | 小説らしい小説。冒頭からチェコらしいリアルで少々グロテスクのユーモアにあふれていて、その上美しく悲しい。クンデラにくらべると絶望感が薄い分だけ悲しみがつきささる。 |
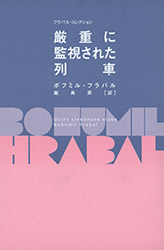 |
第9位 |
池田健二 イタリアロマネスクの旅 | カラー版中公文庫の「ロマネスクの旅」イタリア・フランス・スペインの3部作はいずれも美しい写真と詳しい解説で旅心をそそる。全部で74カ所紹介してるが行った事の有るのは僅か18、この倍は行きたいしイタリア南部に特に心を誘われる。各寺院の記述を読のでいると再訪したくなるし罪作りだ。 | 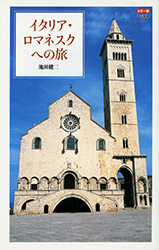 |
第10位 |
中村敦彦 デフレ化するセックス | セックス産業の立地とそこで働く女性の容姿の質と働ける場所、そしてその月収を具体的に詳しく記述している。そしてバブル以来その収入は下がる一方であると指摘、さらにこの産業でも就職は難しくになりつつ有ることを明らかにしている。以前は社会性の低いドロップアウトした人の受皿でもあった業界が、今ではそういう人間をはじいていル様も描かれている。 |
 |
番外 |
JPS Q&Aで学ぶ写真著作権 | 友人が執筆者の1人。写真の著作権についてバランス良く記述されとても有用。まだ曖昧な点についてはその旨書いてあり信頼できる。 |
 |
| ここ数年で一番本を読まなかったが一番本を買った年だった。2013年は買わずに読もう。 | |||
2002 |