私の読書 2013年のベスト10
第1位 |
イスマイレ・カダレ 「砕かれた四月」 | アルバニアの作家イスマイル・カダレの中編読み始めたたら面白くて興奮、20世紀初頭アルバニアの北部山地をバックに血の掟による復習の悲劇を描いたもの、緊張感と冷静さの融合が不思議だ。復習の掟にある「復習が必要になる場合」(例えば一宿一飯の客人でも家の中で殺されたら殺した者の属する家族への復習が必要)「殺し方の厳密な作法」(声をかけずに殺してはならない等)「殺した後の処理」といった細かく複雑なルールに翻弄される主人公の戸惑い、実は復習に逃げ道羽蟻ながらそこにたどり着けない運命、目と目を合わせただけの男女に生じて、それ以上に進まない恋愛が運命の車輪を進ませる。息もつけずあっという間に読了してしまった。緊張感と冷静さの融合が不思議だった。 | 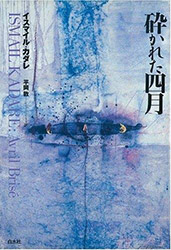 |
第2位 |
チェザーレ・パヴェーゼ 「月とかがり火」 | 岩波文庫の新刊チェザーレ・パヴェーゼの短編集「祭の夜」が素晴らしかったので、パヴェーゼの世界に戻ってきました。大学時代に最も好きだった小説「丘の上の悪魔」を再読「ぼくらの中を裂く女は、もっと後からくるであろう」と始まる青春小説はあの頃と同じく心を打ちました。そこから「月とかがり火」「浜辺」「流刑」「青春の絆」「故郷」「おんな友達」「丘の上の家」と主な小説を皆読みました。いずれの小説にもイタリアの第2次大戦前後のファシズムの圧迫に抵抗する日々、そして戦後の反動の時期の息苦しさが重くのしかかると同時に青春の甘さがからんで美しい。主人公はどこか友人や社会との微妙な距離感があり、女性に対する渇望と不信感があって小説の最後まで切りの晴れない感じがついて回っています。42歳で自殺したために作品が少なくもっと読めないのが残念です。 |
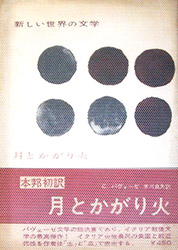 |
第3位 |
ハインリッヒ・マン 「アンリ4世の青春」 |
歴代の王で最も人気のあるアンリ4世は16世紀後半、ヴァロア朝の後を受けて田舎のバスクにあるナヴァール王からブルボン朝初代のフランス王になった。生涯6度のプロテスタントとカソリックの改宗という事により原理主義とは最も遠い人物である事が判る。ハインリッヒ・マンは彼を主人公に続編「アンリ4世の完成」を加えると2段組み1200ページもの大著をあらわした。ナントの勅令を発して両教徒の融和を計り、戦争よりは懐柔によって紛争の解決を図り、財政再建につとめ,国民生活を大切にした王を描く事で、マンの祖国ドイツのナチスを批判したのだった。 |
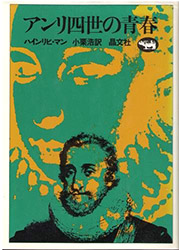 |
第4位 |
宮崎かずゑ 「長い道」 | 80才余の元ハンセン病患者の作者が一生を振り返り著した、限りなく美しい一冊。10才の年瀬戸内海の長島愛生園に隔離されてしまうのだが、それまでの岡山県の山中の貧しい村での家族の愛情に包まれた暮らしを、今体験したばかりの様な鮮やかさで語っていて涙してしまう。 |
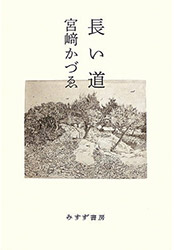 |
第5位 |
ドナルド・キーン 「百代の過客」 | 江戸時代までの有名無名な日記から日本人の興味、感性を抽出した作者の代表作、始めに続編を読んで本編を読んだがどちらもとても面白い。日本人の日記好きによって昔の人の日常に親しめた。なかでも「奥の細道」は文学的につくられた日記で,この場所で欲しい天気、欲しい出会いを創作で描いているという指摘は「目から鱗」であった。 |  |
第6位 |
ネイサン・イングランダー |
ニューヨーク州に住むユダヤ教正統派の親から生まれたが信仰を離れた作者の描く正統派の人々の物語。いかにも厳格そうな戒律を墨守もしながら、戒律の穴を巧みに探したりもする。そのずれの面白さを描くかと思うと、東岸占領地のパレスティナ人とイスラエル人の母親の物語等最も書きにくいテーマから逃げたりしない。真っすぐな視線と斜に見る態度の融合がこの短編集の魅力かもしれない。
|
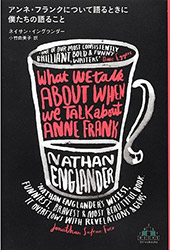 |
第7位 |
レールモントフ 「現代の英雄」 | 高校時代から積ん読だった本を読了、当日使っていた日記帳に月1冊のお勧め本が載っていてそれで求めたのだと思う。ひとたび読み始めると先が知りたい面白さであっという間に読了、冒険小説とフランス風心理小説が絡み合った今まで経験の無い小説だった。語り手は主人公の断片的なエピソードしか語らないため、彼の気持ちを自由に捉えられるところが魅力のひとつなのだろう。全編を貫く重苦しい空気は作者が当時のロシア社会に感じていあことなのかもしれない。レールモントフは決闘を装って政府に殺された。 | 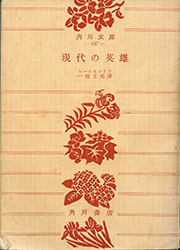 |
第8位 |
トーマス・マン 「ファウスト博士」 | トーマス・マンはおもしろい。暗いという評判だが、音楽と一途に進む主人公はやがて清々しく感じる程だ。芸術家の生き方をその生活から見事に描いていると感じた。 |  |
第9位 |
トルストイ 「幼年時代」 | 文豪トルストイ24歳の時の処女作にして出世作、母をなくすまでの少年時代の思い出を、冷徹な自己批判を持ちながらもなお甘く描いている素晴らしい作品。母を失った時の自分の振る舞いを、見られていいる事を意識しての演技が混じっていると厳しく見つめつつ、母の実家からついてきた忠実な女中の悲しみについて、たっぷり嘆いた後ぱっと切り替えていつものように家事をすると素朴さの中の力強さに感嘆している。透徹した観察力、そして庶民の智慧への賛美、処女作にして後の作品に通底する何もかもがあるように感じた。 |  |
第10位 |
ヴィルヘルム・ゲナツィーノ 「そんな日の雨傘に」 | ドイツの同時代小説、主人公は靴のモニターという稼げない仕事で半ば女性の援助で暮らしているいわゆる駄目中年男だけれどどこかもてる。街で出会う女性、見る物にぶつぶつと不満や妄想や欲望をいつも沸々とさせている。深淵な哲学的な外観をは無いし「意識の流れ」のパロディばりにばかばかしい、と思っているとどこかひきずりこまれる奇妙な味の小説。 | 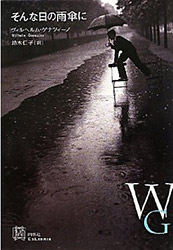 |
第10位 |
フォークナー 「アブサロム・アブサロム」 | しつこくて重くて粘っこくまとわりつくような印象の小説、登場人物はそれなりに外界と関わりながら生きているにもかかわらず、閉じ込められたような空気が小説全体を支配していて息苦しい。癖になるような息苦しさが怖い。 |
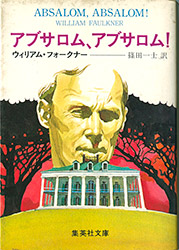 |
番外 |
浜井浩一 芹沢一也 「犯罪不安社会」 | 統計的には戦前よりも、憧れて語られる事ある「三丁目の夕陽」の時代より凶悪犯罪も、一般犯罪も、少年犯罪も確実に大きく減っているのに、人々は治安が悪くなっているような妄想に取り付かれている。重罰化によって犯罪減少は期待できない問題なのに世間的にはそういう風潮が強く息苦しくなっきている現状をよく分析している。印象でなくて根拠で物を言う事を反理性的主義傾向の時代風潮が押しつぶしているのだろうか。 |  |
| 2012年に比べて余計に読んだけれどまだまだ、ほとんどが翻訳小説だった。科学系、社会系ももう少し読みたい。「2013年は買わずに読もう」と年頭にはんざい書いたがやはり積毒は増加、今年の目標も摘んである本を読もうにしたい。 | |||
2002 |