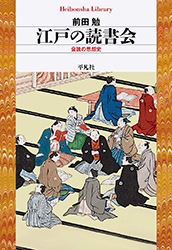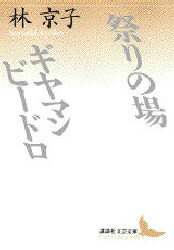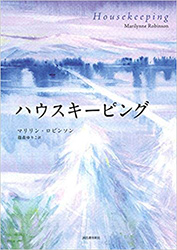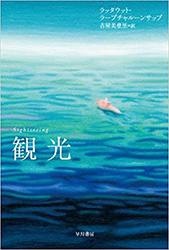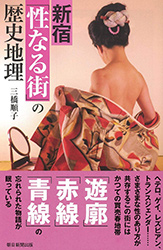私の読書 2018年のベスト10
2019.6.20 更新
第1位 |
前田 勉 |
江戸時代の学問は儒教もその他の分野も、実際の立身出世と関わりがなかった。そこが科挙による人材登用の道のある中国韓国と大きく異なるところだった。受験学問におちいらなかったため、自由で活発な討論があり、身分制を超えて下級階級のものが上級のものに勝てる場所でもあった。たとえ藩主に反論してもお咎めなかった例など豊富な引用で具体的に描写し共感している。 |
|
第2位 |
幸田 露伴
|
幸田露伴はながらく「五重塔」しか読んでいなかったが、後期の作品を読み始めてその面白さに圧倒された。難しい漢字、熟語の連発で、JIS第2水準にもない漢字が出現して辞書を引いてもわからないところもあるのだが、たとえそれが全てわからなくてもべらんめえ調の語り口、リズム感の良さで快く気持ちに落ちていく感じだった。脱線の面白さは寄席の芸を思わせるところもある。 |
  |
第3位 |
ジェラード・ラッセル,
|
イスラム一色と誤解される中近東では小さな宗教が多数生き残っていて、ユダヤ教以外を根絶やしにしたキリスト教世界と大きく違う。それらの宗教を暮らす人たちを実際に尋ね厳しい近況を報告するイギリスの外交官の作者の公平な目がすばらしい。 |
|
第4位 |
石光 真清
|
高校の副読本に一部引用されていた「城下の人」を初めて全編読み、大変におもしろかった。熊本藩の下級藩士ながら実力により重要な仕事をしていた作者の父は武士の世が終わることを見通していたようだが、西南戦争の西郷軍の熊本占領時、まだ少年だった作者は武士道に燃えむしろ復古的で時代が見えていなかったことを素直に書いている。 これは4部作で、東京に出て士官学校入学から、こころならずも陸軍の情報将校として中国東北部をかけめぐり、帰郷退役して郵便局長をする晩年までがえがかれている。やはり白眉は第1部だが、大陸の日本軍の未定見、右往左往がかかれている3冊も読むに値するものだった。 |
 |
第5位 |
林 京子 |
長崎原爆の被爆者である作者が自ら体験を虚飾、妥協無しで描ききっていて迫力に満ちている。書かざろう得なくて書いた本と言うことが伝わってくる |
|
第6位 |
スティーヴン・D・レヴィット
|
裏の仕事も人材、努力、マーケティング等々、表の企業と同じ努力をしていることがわかるし、裏の仕事でも階層や人種の違うところに食い込むには同じような障害があるという最もすぎる話が無性におもしろい。人間がしっかり描写されているからだろう。 |
|
| 第7位 | フラバル
|
フラバル大好きです。これも面白く物悲しい。 |
|
第8位 |
マリリン・ロビンソン
|
美しく悲しい | |
第9位 |
ラッタウット・ |
タイ系アメリカ人の作者の素晴らしい短編集 | |
第10位 |
榎原 雅治
|
中世の道や宿場はその時の政治状況、また今では考えられないことだろうが、当時はしょっちゅうあった川の流路変更などで位置が変化している。名古屋近辺を中心に具体的に説明している。歴史地理学は楽しい。 | |
番外
|
三橋順子
|
これも歴史地理学の研究書、表紙はセクシーだが中身は硬派。復元しようと試みるのは公認非公認の新宿の売春地帯だが、古地図、航空写真、色々な資料に残る写真を証拠に場所を特定していく。新宿区民であるレビューワーにとっては今はなくなった道、都電、建物を思い出し懐かしい。赤線廃止の時は小学校3年だったが。 |
|
| 番外 | 小島政二郎
|
久保田万太郎の小説は遥か昔「三の酉」を読んだだけだが、小島政二郎は彼は俳句の方が良いと宣告する。確かに軽妙で東京的で共感できた。 | |
| 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
2002 |