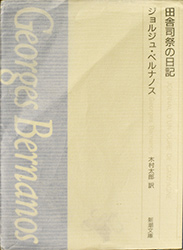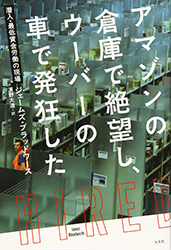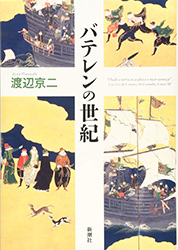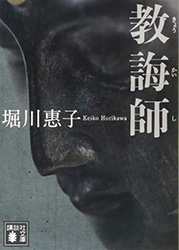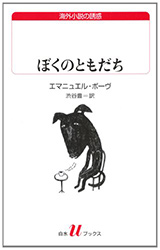私の読書 2019年のベスト10
2020.3.25 更新
第1位 |
ベルナノス |
あまりに自らに誠実で他人には不器用な新任の司祭の話となると道徳的教訓的な小説と捉えられそうだが、題名の与える印象とは真逆の熱にあふれた小説で引き込まれた。最も頑なな人の心を溶かす何かが彼にはありその過程の描写が心を揺らす。少数の理解者を彼は得るのだが、過激な自己批判と広い教区の負担から徐々に体が蝕まれてゆく。登場する貴族から聖職者、医師、庶民、若者にいたるまで、リアルに複雑でまさに今生きている人間に描かれていた。 |
|
第2位 |
ジェリー・Z・ミュラー
|
企業や学校、病院、警察など実績を測定し、それによって金銭的な報酬や昇進等を行うことははなはだ理にかなったことのように思われる。説明責任、能力給等々の言葉は新しい革新のように考えられている。 |
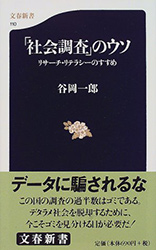 |
第3位 |
バルガス=リョサ
|
今まで読んだことのないような手触りの小説だった。消息をたった学生時代の友人が現地の先住民族の中に生きているという情報で探しに行くが、先住民族と文明社会の根本的な矛盾にであい語り手は混乱していく。語られる民話の肌合いも文明化された童話とは全く違う不可思議でむしろ無常理といった味だった。 |
|
第4位 |
イングボルグ・バッハマン
|
繊細で感受性の強すぎるけれど情緒的ではない主人公の述懐はチリチリしていて、人の醜いところを自然と抉り出していて思わず読み進んでしまう。
|
|
第5位 |
ジェームズ・ブラッドワース
|
イギリスのEU離脱、トランプ当選などは、いまま労働党や民主党を支持していた庶民の働く人々が、彼らの住む世界が脅かされていると感じて離反したことが実感としてわかる本だった。 |
  |
第6位 |
渡辺京二
|
愛読している渡辺京二の厚い1冊、キリシタン到来から、宣教師たちの組織と個々の人となり、キリスト教の受容と反発、最後は天草の乱まで世界史的観点から叙述していて大変に面白い。 |
|
| 第7位 | 山室信一
|
「王道楽土」たらんと標語を掲げた満州国の実態を冷静かつ厳しく解剖していて納得できた。満州国民とはなにか、国籍法がないため満州国民は誰だかわならないのだ。日本人で満州国民になったものがいないと同時に、五族協和をかかげられた他の4つの民族も満州国民ではなかったということになる。
|
|
第8位 |
堀川惠子
|
死刑囚の教誨師を50年間つとめた真宗の僧侶渡邉普相から長い間話を聞き続け書かれた1冊。 |
|
第9位 |
飯島耕一
|
江戸時代の儒学者の友情の物語と、現代の一人の女性をめぐる回想がいきつもどりつする詩人飯島耕一の小説。雑誌連載中に中断したかで読み切れずに気になっていたが単行本になり読むことができた。のんびりとした感じが良い。 | |
第10位 |
劉慈欣
|
中国のSFのパワーに圧倒された。政治状況の描写も面白い。続編のあと2作の翻訳が楽しみ。 | |
番外
|
エマニュエル・ボーヴ
|
自意識が高くて不器用で貧しい男の悲しくもおかしな日常。自分にも思い当たるところがどこかにあってくすぐったい |
|
| 番外 | 井上章一
|
権威を打破するのがこんなにも大変なのか。桂離宮はそんなに素晴らしいのかという視点で再検討した説得力のある一冊。中では丹下健三のエピソードが面白い、見に行くとこんなものかつまらぬと思うけれどまた気になってくるとのこと。 私も一度見に行って修学院離宮の方がいいじゃないという感想だった。ただ写真集は圧倒的に桂離宮を撮ったものが面白い。現代の建築で権威ある賞を取ったもので写真も素敵なのでも行ってみるとつまらないと感じることがままある。結局インスタ映えと通底していて、写真や図面、模型の方が素敵という建築なのではないかと思った。 コルビジェ神話についても書いて欲しい。 |
|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
2002 |